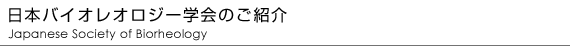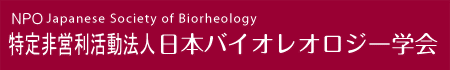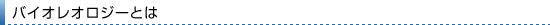
�p���^���C�Ƃ������t������܂��B�M���V���̓N�w�҃w���N���C�g�X�iBC 540 - 500�j�����������t�ŁA"�����͗��]����" �Ƃ����Ӗ��ł��B�嗤��X�͉͂��疜�N�A�����N�̊Ԃɂ͏������ړ����܂����A�t�ɐ��Ȃǂ͂����Ƃ����܂Ɉړ����ė���Ă��܂��܂��B�ő̂Ǝv���镨���������Ԃ����Ċώ@����A�t�̓I�ɐU�镑���܂��̂ŁA�ǂ̒��x�̃^�C���X�P�[���Ŋώ@���邩���d�v�ƂȂ�܂��B
���I���W�[�́A��ʂɂ� "�����̗����ƕό`�̉Ȋw" �ƒ�`����Ă��܂��B���I���W�[�Ƃ������t�́A1930�N���납��g���͂��߂܂����B���I���W�[�irheology�j�̃��I�irheo�j�́A�M���V����Ł@"����"���Ӗ����܂��B���I���W�[�̌����́A�����q���w�A�h���A�����Ȃǂ̍H�ƕ���ł̌����A�Z�p�̐i���ƂƂ��ɔ��W���Ă��܂����B
����A�o�C�I���I���W�[�ibiorheology�j�́A���̂���ѐ��̂��\�����镨���̗����ƕό`�̉Ȋw�Ƃ������Ƃ��ł��܂��B���̂���ѐ��̂��\�����镨���Ƃ������ƂŁA�l�Ԃ��܂ނ��ׂĂ̓����ƐA�����ΏۂƂȂ�A�������\�����镨���S�Ă��ΏۂƂȂ�܂��B�Ⴆ�A���t�A���ǁA�S���Ȃǂ̊e����A���A�畆�A�є��A�ؓ��A�זE�A���̔S�t�A����ς�����DNA�n�t�A���邢�͂ł�Ղ�A�[���`���A���V�A�~���N�A�`�[�Y�Ȃǂ̐H�i�A�r�т▃�Ȃǂ̓V�R�@�ۂȂǁA�����̓��퐶���ɊW�������̂��l�����܂��B
�o�C�I���I���W�[�͈�w�Ƃ��[���W���Ă��܂��B���ǁA���t�A�e�푟��A�e��튯�̕a�Ԃɂ����郌�I���W�[�����A���I���W�[�I�ȗ��ꂩ��̊e��튯�̕a�Ԕ����Ƃ̋@�\�̉𖾂ȂNJ�b����їՏ���w�ɂƂ��Ă��d�v�ȉۑ肪��������܂��B�Ⴆ�A�����d���⓮��ᎂȂǂ̌��Ǖa�ρA�����ǁA��������z��Q�A���z�Ȃǂ����ɍL���͈̖͂�肪�����̑ΏۂƂȂ�܂��B
�o�C�I���I���W�[�̓o�C�I���J�j�N�X���p�H�w�̌�������Ƃ��֘A���鋫�E�̈�̊w��ł��B���܂蕪��⌤���e�[�}�ɂƂ��ꂸ�A�������ۂ��邢�͐��̂��\�����镨�����A�H�w�I��@��p���Č������Ă��錤���҂̏W�܂肪�{�w��ł���Ƃ����܂��傤�B
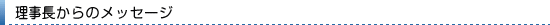
�@�{�N6���̔N����������{�o�C�I���I���W�[�w��̑�23���������ɏA�C�������܂����B�������̒ʂ�A�{�w��̓o�C�I���I���W�[�����̃p�C�I�j�A�ł��鉪 ���V�搶�i1907?1990�j�����S�ƂȂ���1977�N12���ɐݗ�����܂����B���̗��������͂��߉���̊F�l��45�N�ȏ�ɂ킽��a���ł���ꂽ�P���������j�A��������Ă����f���炵���`����������ɔ��W�I�Ɍp������ׂ��s�͂������Ƒ����܂��B�o�C�I�͐�����\���A���I���W�[�͕����̗����ƕό`�������w�╪���\���܂��B���Ȃ킿�A�o�C�I���I���W�[�́u���̂���ѐ��̂��\�����镨���̗����ƕό`�̉Ȋw�v�ƒ�`���邱�Ƃ��ł��܂��B�v�f�Ҍ��_�̗���ɗ��ƁA�������ۂ͂�����\������זE�A���q�A��`�q���x���̕����E���w�I�����ɂ������ł���A�Ƃ���܂��B�u�������ۂ̃_�C�i�~�Y���v�ƌ�����悤�ɁA���̌���͂��������f�ߒ��̃_�C�i�~�N�X�ɂ���܂��B�����̒�`�͓��O����ʂ���זE�̊����ɂ�莩�ȑ��B����ё�ӂ��s�����Ƃł����A�����_�C�i�~�N�X�̂�����̖{���͂���ɊO�E�ւ̓K�������Đi���ł���ƌ����܂��B���Ȃ킿�A�������ۂ͕��ՓI�ȑ��ʂ�������ő��l���ɕx��ł���A���̗����ɂ͊w�I�iTrans-disciplinary�j�Ȍ������s���ł��B�{�w��̎�舵����b�w��̈�͈�w�A�����w�A�H�w�A���w�Ȃǂ��܂݁A�����Ώۂ͌��t���I���W�[����H�i�H�w�܂ő���ɂ킽��܂��B�o�C�I���I���W�[����������ɐ[����������悤����̊F�l�ƂƂ��ɁA�e�X�̊w��̈�ɂ�����u�m�v�����W���āu�����m�v�����A�{�w����o�C�I���I���W�[�́u�����m�̏�i�v���b�g�t�H�[���j�v�Ƃ��Ĕ��W�����Ă��������Ƒ����܂��B
�@�u�����͗��]����iPanta Rhei�A�p���^�E���C�j�v�Ƃ��������Œm����Ñ�M���V���̎��R�N�w�҃w���N���C�g�X�́A�����̕ω��͑Η��ɂ���ċN����A�����Ɍ�����v�f���Η����邱�Ƃŕω������܂�邪�S�̂Ƃ��Ă͒��a��ۂ��Ă���A�ƍl�@���������ł��B�������ۂɂ��A�����ƈى��i�����ƕ����j�A���k�ƒo�ɁA���B�ƌ����ȂǑ�������@�\�����݂��邱�Ƃ́A�w���N���C�g�X�̂��̎�����z�N�����܂��B�w���N���C�g�X�̎��R�N�w�v�z�́A���R�A�l�Ԃ␢�E�̍��{������[���T������N�w�̊�b��z�����N�w�̑c�ƌ�����\�N���e�X�A�N�w�I���߂�ʂ����̌n�I�����ɂ���đ����̉Ȋw����̊�b��z�������w�̑c�ƌ�����A���X�g�e���X�ɉe����^�����ƌ����Ă��܂����A2,500�N��̎��B�ɂ��e����^���������l�́u�m�v�ɋ����ƌh�ӂ��������ɂ͂����܂���B�\�N���e�X�̒�q�ł���v���g���̓A�e�l�x�O�̒n�u�A�J�f���C�A�v�Ɋw����݂��A����͌��݂̌����@�ւ�\���u�A�J�f�~�A�v�̌ꌹ�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ͂����m�̒ʂ�ł��B�w�[�Q���ɂ���Ē莮�����ꂽ�ُؖ@���Ñ�M���V���N�w�ŏ��߂ēo�ꂵ�܂����B�{�w��̓��F�́u���l�����ۂ����v�ł��邱�Ƃł��B�w��̋c�_�ɂ����ĈقȂ闧��A�قȂ錩��������ꍇ�́A�ُؖ@�I�ɂ�荂�������̍l�@�ւƐ����W�J���邱�Ƃ��ł��܂��B�M���V���̌��l�B�������̖{���ɔ��낤�Ƃ����悤�ɁA���I���W�[�̗��ꂩ��u�������ۂ̃_�C�i�~�Y���v��T�������������Ƒ����܂��B
�@�{�w��ł́A���Ǔ����ÁA�z��n�_�C�i�~�N�X�Ǝ����A���t���I���W�[�Ɣ����z�A�זE�E���q�̃��J�m�o�C�I���W�[�A�e�B�b�V���G���W�j�A�����O�E�l�H����A���̕����̍\���`���Ƌ@�\�����E����A�H�i����у\�t�g�}�^�[�̃��I���W�[����v�e�[�}�Ƃ��ĐϋɓI�Ɏ��g��ł��܂��B�w����Ƃ��āA���{�o�C�I���I���W�[�w��N��A�o�C�I���I���W�[�E���T�[�`�E�t�H�[�����A���I���W�[���_��i���{���I���W�[�w��Ƌ�����Áj���J�Â��Ă��܂��B�܂��A�w��Ƃ��Ęa���w�B&R����щp���w�Journal of Biorheology�����s���Ă��܂��B����ɁA���ۓI�����Ƃ���The International Society of Biorheology�Ƌ������AESCHM (The European Society for Clinical Hemorheology and Microcirculation)-ISCH (The International Society of Clinical Hemorheology)-ISB (The International Society of Biorheology)��3�w������ۉ�c�ɉ^�c�ʂ��܂߂ĐϋɓI�ɎQ�悵�Ă��܂��B���������w����ɂ����āA�o�C�I���I���W�[�����̏�����S����茤���҂̈琬�A�����O�Ɍ������ϋɓI�ȏ�M�͋ɂ߂ďd�v�ł��B�{�w��̂���Ȃ锭�W�̂��߁A����̊F�l�̂��x���E�����͂�������낵�����肢�\���グ�܂��B
| |
NPO�@�l ���{�o�C�I���I���W�[�w��
�������@�勴�@�r�N
�k�C����w��w�@�H�w�����@�E����
Email: ohashi��eng.hokudai.ac.jp
�ߘa5�N11��1��
|